羽織の紐のたけって…?
五月は「子どもの日」やら「端午の節句」やらがあるので、童謡や子どもの歌を聞く機会がなんとなくあります。
ショッピングセンターや催事場なんかで「せいくらべ」の歌もよく耳にします。
歌詞を覚えてますか?
はしらのきずはおととしの
ごがついつかのせいくらべ
ちまきたべたべにいさんが
はかってくれたせいのたけ
きのうくらべりゃなんのこと
やっとはおりのひものたけ
何気なく聞いていたけど、よくよく考えると意味がよくわかんないんですよね。
ちょっとひも解いていきましょう。
柱の疵(きず)は一昨年の
五月五日の背比べ
まず、ここまで。
一昨年の五月五日に、背の高さを測って柱に疵がついている。
今はピンとこない出来事ですが、「子どもの日」に背丈を測って柱に目印をつけるというのはよくあることでした。
兄弟姉妹で順番に背を測っては柱に書き込む。
それで、「すごく伸びた」だの
「弟に(背の高さを)抜かれた」だの
わーわー、やってたわけです。
だから「背丈を測る」ではなく「背比べ」なんじゃないでしょうか。
昭和の高度成長期以前は兄弟姉妹の数が多かったので、さぞかし賑やかだったでしょうね。
古き良き日本の家庭の情景ですねぇ。
では次の2行
粽(ちまき)食べ食べ、兄さんが
測ってくれた背(せい)の丈
五月五日の「端午の節句」には粽を食べる風習があるので、お兄さんが粽を食べながら背丈を測ってくれたんでしょう。(お行儀がいいとは言えませんが)
さて、問題は最後の2行です。
昨日、比べりゃ なんのこと
やっと羽織の紐の丈
「昨日、比べてみたら、なんてこった
(今の自分が着ている)羽織の紐の高さくらいしかないよ。
ちっちゃかったんだなぁ。僕。」
って、勝手に解釈してました。
でもね、2年でそんなに大きくなる?
と、ふと疑問が生じたわけです。
今の時代、一般的には着物の生活をしていないので、これまたピンときませんが、旅館に泊まったときに浴衣の上に着るヤツ、あれが羽織。
「ホテルにしか泊まったことないよ」という人は実際に着たことがないかもしれませんが、落語家さんや、お相撲さんを見れば「ああ、あれね」とわかるはず。
羽織の紐を結んでいるのは、お腹の上。
みぞおちあたりですかね。
とすれば、この男の子は「おととしから昨日」までの間に、「みぞおちから頭の先まで分」背が伸びた。
ということになります。
成長期でもそんな伸びるかなぁ?
軽い気持ちで書き始めたら、長くなっちゃたので(後編)に続きます。
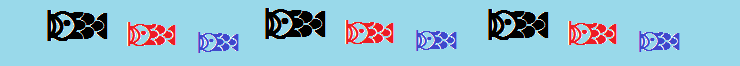
◎「せいくらべ」
作詞:海野厚(うんの あつし)
作曲:中山晋平(なかやま しんぺい)




🐧 コメント欄 メールアドレスは公開されないので気軽に書いてください